企業が避けられない“持続可能性”のリアル…SDGsはきれいごと?
- KOBAYASHI

- 2025年11月15日
- 読了時間: 3分

きれいごとから参入条件へ
SDGsやサステナブルという言葉は、耳障りの良いスローガンのように扱われがちです。でも、利益や納期が最優先の現場では「そんな余裕はない」と感じる人も少なくありませんね。しかし現実には、取引先の調達基準や人材採用の応募要件、融資や補助金の審査項目にまで、持続可能性の姿勢が食い込んできています。
いまやSDGsは広報戦略ではなく、事業を続けるための前提条件に変わりつつあるのです。
コストではなくリスクの回避
企業が環境配慮を「余計なコスト」と見なす時代は終わりつつあります。法規制の強化や、廃棄物処理に関するトラブルによるブランド毀損は、目に見える損失をもたらします。
逆に、持続可能性を組み込むことで、調達リードタイムの遅延を避けたり、エネルギーコストを安定化させたりすることが可能になります。視点を変えれば、持続可能性は守りの出費ではなく、未来の損失を抑えるための投資に近いものです。
循環を前提にした発想
サステナブルを単に「捨てない努力」と捉えると、社内に負担が増すだけです。本質は「循環を前提に設計すること」にあります。調達時点から修理のしやすさや再配備のしやすさを考慮するだけで、ライフサイクル全体の足跡を小さくできます。
オフィス備品や制服、そしてIT機器まで、すべては循環のスタート地点として見る必要があるのです。
IT運用にこそ潜むチャンス
持続可能性というと電力や物流が真っ先に思い浮かびますが、実はパソコンや周辺機器のようなIT運用領域はもっともサーキュラーな現場です。
調達から利用、再配備、廃棄に至るまでサイクルが早く、数も多いため、改善効果がすぐに現れます。重要なのは「最新が正しい」という思い込みから離れ、業務要件を満たす十分な性能を軸に選ぶことです。
その転換こそがエネルギー消費と廃棄の両面を抑え、さらに調達リスクの低減につながります。
小さな一歩が積み重なる未来
持続可能性は壮大なテーマに見えても、始まりは小さな行動です。社員が電源設定を意識的に変えることや、返却されたパソコンを再設定して次の人へ回す仕組みを作ること。
こうした一歩が積み重なると、企業の姿勢そのものとして外部に伝わっていきます。いまの社会は、その姿勢を確かに評価し、選別しているのです。
若い世代の就職活動においても、投資家や取引先の判断においても、環境に鈍感な企業は真っ先に外される傾向が強まっています。だからこそ、循環を前提にした設計と正直な情報開示を積み上げることが欠かせません。その具体的な実践例の一つとして、アップサイクルされたパソコンをレンタルで利用するという形も存在しています。
これは解決策のすべてではありませんが、確かに現場で役立つ選択肢の一つです。

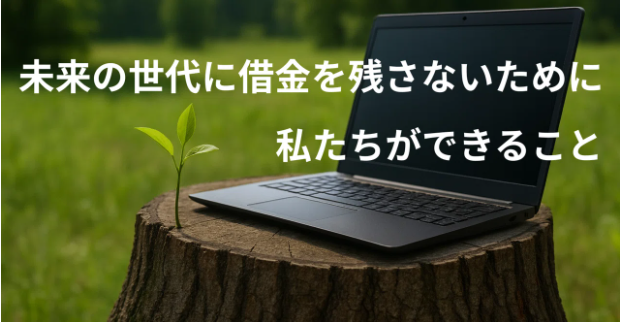


コメント